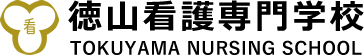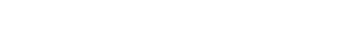令和7年7月22日(火)
1年生の授業風景です。
この日は冷罨法(れいあんぽう)と温罨法(おんあんぽう)について実践的に学ぶため、第1実習室で授業が行われました。
”冷罨法” 氷枕を用いた冷罨法を実践&体験
最初に先生のデモンストレーションを見たあと、グループにわかれて氷枕を作成。
枕に入れる氷や水の量、クリップで枕の口を閉じる時の注意点など、先生の説明を思い出しながら作っていきます。




氷枕が出来上がったら、順番にベッドに横になって体験。水滴でベッドが濡れないよう、氷枕はタオルにくるんで使用します。
枕の中の氷が徐々に溶け、氷の角がとれてくると、氷枕の使用感もより良いものになっていきます。
罨法は、疼痛や炎症を起こしている部位の緩和を目的とする技術ですが、暑い季節、心地良い冷たさに触れ、みんな気持ちよさそうでした。


”温罨法” 温湿布を用いた温罨法を実践&体験
冷罨法の実践・体験が終了したら、次は温罨法です。
先ほどと同様、先生のデモンストレーションを見たあと、グループにわかれてタオルで温湿布を作成。
お湯の温度、タオルをお湯に浸ける際のコツや注意点など、先生の説明を思い出しながら作っていきます。




温湿布が完成したら、冷めにくくなるようビニール袋に入れ、順番に体験です。
慢性的な痛みや冷えがある場合には、その箇所へ。ない場合はリラックスできる部位にあてるのも良いです。
また、温湿布の上からタオルをかけてあげると、保温効果が上がり、広範囲に温かさが広がります。
リラックス効果で思わず眠ってしまいそうになる学生もいたようです。




お腹の音を聴診しています。
罨法は身近に使える技法ですが、冷罨法であれば凍傷、温罨法であれば低温熱傷を引き起こす場合もあります。
また、疼痛や炎症のタイプによって、冷罨法と温罨法どちらを行うべきかの適切な判断も必要です。
患者さんに行う場合には、十分留意しましょう。